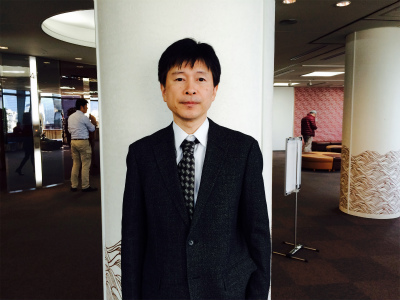――先生は研究者として様々な研究活動をしてこられたと思います。そのなかで先生ご自身の研究の魅力についてお聞かせ願えますか?
一つは修士論文の時から気になっていたストレスという言葉ですね。突然心理学に近いところにストレスという言葉が現れたという感覚がありました。僕は新聞記事を遡って,ストレスという言葉がいつ最初に現れたのか,広辞苑だと第何版から今の定義が現れるのかを調べたんです。心理学って時々,流行り言葉が現れて,みんな何となくのイメージをつけながらやると思うんですけれども,そのこと自体すごく面白い感じがして。卒論の時はアイデンティティという言葉を何でみんな使うのかに関心があったし。ストレスに関しては,ストレスの測定法などという前に人々がストレスという言葉で何を表そうとしているのかに関心があったんです。だから,過去のデータを掘り返して,そこからストレスのナイーブセオリー,素人理論にあたっていくんです。今だとテキストマイニングの手法になるはずなのですが,当時は全部手でやりました。新聞の読者投稿欄にしぼって,ストレスがどんな言葉と一緒に使われているのかを全部書き出したんです。1945年くらいから新聞記事はあるんです。それを書き出すと,人々がストレスという言葉をどんな文脈で使っているのかが見えてくるんです。当時は「ストレスがたまる/ある」という言葉があって,「ストレス解消/発散」あるいは「ストレスで爆発する」という言葉があって,怒りと近いような感じで蒸気機関のように,溜まって圧縮して爆発して,圧力がなくなるみたいなストーリーを,手作業でやったんですよね。
出来上がった概念を使って行動を説明するよりも,概念が出来上がる過程や,それを維持している仕組みにどうも関心があるみたいです。そこはいつも自分が面白いと思うことのようですね。
――ボトムアップに立ち上げて現象を理解していくということですね。
そうですね。そんなことをやっていたから,自分が分析手法の好みとして質的研究と量的研究の間くらいのところを結局狙ってしまうみたいで,一時,名古屋大の大谷先生からは「キセル研究者」って呼ばれていたんです。
――なんですかそれ?
質的研究と量的研究をつないでやる人っていうあだ名というか。質的なデータを数学を使って整理しなおして,中核的なコンセプトとそこから人々が使うバリエーションみたいなものを見ていく発想が僕にはハマりがいいみたいですね。
高齢者の仕事では,そこにもう一つ身体の問題がすごく大きな意味を持ちました。でも,結局そこから生物学的に降りて行きはしなくて,身体がつくり出す意味や,身体が僕らを不自由にさせたり自由にさせたりすることに関心があったので身体をめぐる意味にむしろ関心があるんだろうなと思います。
――現在,先生が主に取り組んでいらっしゃる研究についてお話いただいていいですか?
立場上自殺予防に関する仕事がたくさん占めています。一番時間をかけているのは自殺予防教育プログラムです。中学校のためのプログラムを作っています。教育の場面に持っていくのは怖いとか危ないとかという認識があるなかで,学校でもできるものというニーズに応えようと思い作っています。今までは仕事的に学生とか大人を対象にしていたので子供向けの発想を改めてやると思っていたよりずっと難しいなと思ったりして。子どもに伝えるプログラムを作るんだけども,大人に納得してもらうストーリーが必要で,それは今の社会情勢や,そもそも日本人が死とか自殺とかをどういう風に考えているかに関わる問題で,すごく複雑な応用問題なんです。
あと,自殺予防の枠組みを使った幾つかの仕事があって,例えば,被災地の今後の中長期的な支援の中で自殺予防の視点をどうやって入れていくべきなのかというようなことで,東日本大震災以降ずっと関わり続けています。社会と調査や研究は常に接点を本来もって自殺予防の枠組みはいつもそこに敏感にならざるを得ないんです。スティグマや偏見の問題とか,人々のためらいとかがあるところの仕事なので。面白いとも言えるし難しいとも言えるんですかね。
――先生が研究者を志すきっかけは何かありましたか?
難しいですね。これという決断があったというより,割と最初から研究者になるかなと思っていました。ただ,迷った時期はなくはなくて,公務員試験を受けてみた後に,大学院試験受けて,大学院へ行ったので,研究者にならなかったっていう可能性はありました。
――先生が研究者になってよかったと思ったことはありますか?
研究者っていう言葉の中に,多くの場合大学教員が前提になることが多いと思うんですけれども,僕,大学教員はほとんどやってないんです。早稲田の助手の数年以外は研究所にいたんですよ。研究所では研究に対する意味づけがちょっと違っていて,社会的なミッションと組織が強く結びついていることが多い。早稲田大学の時に僕が色んなことが楽しめたのは,大学の自由さみたいなものが裏に返せばあったんですけれども,研究所はむしろ,今この研究をすべきだというのがあるんです。だから,東京都老人総合研究所の時ならば,介護保険が導入される前で,ただし社会は高齢化が進んで行くときに,特別養護老人ホームで色んな支援が必要なお年寄りたちに対する仕組みが必要だけれどもうまくいっていない,これを解決しなければいけないみたいな社会的なミッションがあり研究をするということでした。今の精神保健研究所も,もともとは厚生労働省の下の研究所ですから,行政的に必要なテーマがあり,それに対して研究をするスタンスになります。研究者になってよかったと僕が感じるのは,社会的な必要性やミッションに対して自分なりの答えを探して,それなりの提案ができることの手応えにあるかなぁって思いますね。
――パーソナリティ学会自体は,先生にとってどのような場として機能していますか?
僕,パーソナリティ学会の学生発起人の一人なんです。学会ができるときに中核になった当時の重鎮の先生と学生を含めて,東京都立大の中に胎動みたいなものがあったんです。僕からしてみると新しい動きとか新しい考え方として立ち上がった学会というのが最初の魅力なんです。あくまで相互作用や関係性のなかにパーソナリティを見ようとする議論が白熱している頃だったので,その新しさですかね。性格が個人のなかで安定しているという基本的な考え方から少しはみだそうとしているのが,当初とても魅力的に感じるところでした。
――では,パーソナリティのどのような点に関心をお持ちですか?
今,パーソナリティという言葉が僕にとってどんな意味があるかというと,パーソナリティという言葉が今の社会にどんな意味をもつのかということだと思います。例えば,ボーダーラインパーソナリティ障害という疾患名で用いるパーソナリティとパーソナリティ心理学会がいうパーソナリティには,概念の連続性よりも使い方の連続性をすごく感じるんです。「あの人は病気というよりも,その人の個性が平均値よりも極端に偏っているんだ」っていう,パーソナリティ障害の考え方と,パーソナリティ心理学会の学会発表で何々パーソナリティと呼ばれているものとの間の距離が,年々近づいてきているような気が僕はしているんです。そういう意味でパーソナリティという言葉が照らす社会性や,人々の営みが僕にとって関心があるところかなと思います。最近レジリエンスという言葉を使う人がすごく多くて,ストレスと同じようにまた始まったなというように楽しんでいるんですけど。
新しい考え方とか概念が個性として位置づけられて,それが人や現象を理解するためのツールになっているときはいい。けれども,それが反転して人を選別し,位置づけ,場合によってはそのことで優劣を決めてしまうような事態になっていくといううねりを何回か通っているような気がしているんです。多分,学会がそれに対するある種の自浄能力みたいなものを示すのかなと思っていますね。個性とか人を理解することが人を分けたり決めつけたりすることではないんだっていう。そういう機能を果たすところとしてパーソナリティ心理学会が期待されるし,そこに関わることの意味なのかなって思うんです。
――今後の活動としてパーソナリティ心理学会の未来的な展望としてどういうところに期待しますか?
パーソナリティ心理学会に限らず,日本の学会あるいは研究者の人が海外と交流することが昔よりずっと盛んだし,積極的になってきていると思うんです。それは,土台がないとできないことで,例えば学会が海外の研究者を呼ぶことが入り口になることもあるし,学会という母体とか,共通するパーソナリティというキーワードで交流ができることは,それがない時と比べると圧倒的に楽だったり,チャンスが拡がったりということがあると思うんですよね。
ストレスとかレジリエンスとなどの言葉は,結局海外でその意義が見つけられるわけですけど,その気づきはメタファに近い。割とぱっと決まってそれから練られて,練られたものが日本にやってくる,だけど,日本もまた色んな使い方をしていて,うまく展開する場合もあるし,まずい方向に機能する場合もある。そういう成り立ちや変化のプロセスを,僕が初期の頃にやったみたいに新聞を紐解くよりも,海外の研究者とコミュニケーションすれば,さらにその前のところがわかるわけですよね。そういう意味でいうと,僕にとって学会に期待することは視野と交流を広げる場なんじゃないかなと思うんです。もしかすると僕よりも若い人の方が学会なしでも,パーンと広げていけるのかもしれないですけど,だけど土台があって,先輩たちがつくったネットワークがあって,そこに若い人がさらにのっかっていって,新しいもの見つけていくことが,科学的概念ですら偏ったり歪んだり,あるいは様々な作用を及ぼすことを考えると,できるだけ色んな機会を利用して,それを相対化したり深める作業がすごく大事なことだと思うんです。だから,パーソナリティ心理学会も,パーソナリティの枠組みのなかでそういう機会であるべきだろうと。内部での交流ももちろん大事ですけれども,内部の交流を土台にして,共通する他の学会とか,共通する海外とかに広がっていくための重要なステップボードになることが大事なことじゃないかと思います。
――お話に関わるかどうか分からないのですが,第一回の性格心理学会から呼びかけセッションっていうのがあって,結構共通することなんじゃないかと思いました。
そうですね。若い学会だったので色んな企画を考えていて,今だとヤングサイコロジストのような機能ですよね。色んなチャンスをつくって,呼びかけセッションは,「今,私はこんなテーマに関心があるんだけれど,誰か一緒に共同研究をやりませんか」ということのためにスタートしたと思うんです。すごく悩むんですけど,一人でじっと考えて深める作業が本来僕好きなんで,若い頃はあまり学会なんて出なくてもいいと思っていたことも実はあるんです。でも,今の歳になって思うと,学会が提供するチャンスを活かす方が,広い眼で見たときにいい仕事になっていくと思うんです。本来社会現象とか,心理学が扱う現象ってかなり社会文化的に色んなバイアスを受けながら成り立っているものだと思うので,それをうまく整理しつつ,多様な変数を考慮に入れていくための土台として学会はとても大事なんじゃないかなと思うんです。 でも,逆に注文をつけるとしたら,心理学にとどまらずに色んなところに学会が踏み出してほしいなっていう思いもなくはない。心理学はアメリカなんかみても,活動の場がたくさんあるじゃないですか。日本でももっと食い込めるところがたくさんあると思うんです。やっている人はもちろんやっている。ただ学会全体としてもっと積極的でもいいなって感じますね。
――川野先生には,京都にご出張中の合間をぬってインタビューに応じていただきました。実際は1時間半におよび丁寧に具体的にお話くださり,せっかく頂いたお話を編集せざるをえなかったことは心苦しい限りでした。先生方が築いてきてくださった学会が与えてくれるチャンスをうまく活かして,私も研究を展開していきたいと強く感じました。川野先生,本当にありがとうございました。